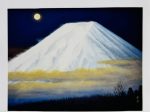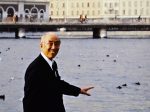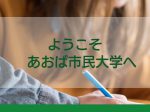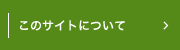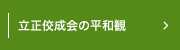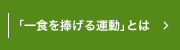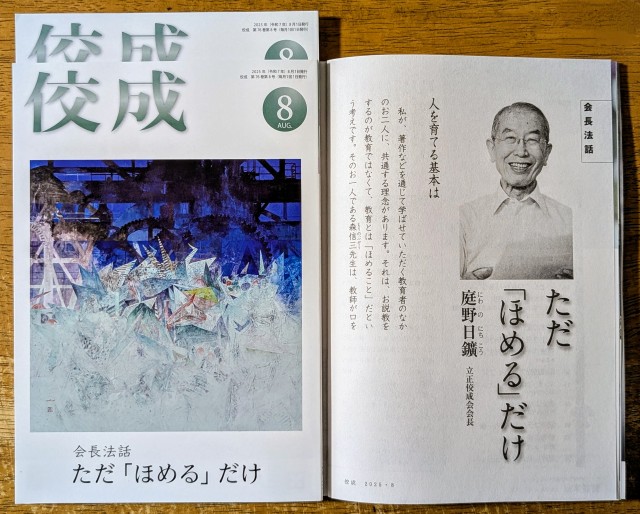
今夏は、8月の夏本番の以前より「夏なつ夏なつココはもう夏」という感じです。七夕かざりを揺らす涼風が恋しいですね。夏の睡魔の吹き飛ばせ、東北の三大祭り(「青森ねぶた」「秋田竿燈」「仙台七夕まつり」)の起源は、七夕の「眠り流し」、7月7日の夜に川や海に穢れを流す灯篭流しや灯篭送りが変形したものと考えられています。七夕行事の一つ、秋の収穫前に労働の妨げになる睡魔を追い払うため、人形などに睡魔を委ねて祓い流す「眠り流し」という習慣が様々な祭りに発展して~仙台の七夕は、本来はお盆を迎える前に禊の行事だったようです。
『佼成』8月号の会長法話 ただ「ほめる」だけ
・人を育てる基本は
森信三先生は「たとえば、学校の下足箱で靴のかかとが揃えられていなかったら、生徒の見ていないときになおしておくのが教師の仕事であって、そうすると下足箱の靴のかかとが少しずつそろいはじめるので、そのとき、教師はそれをほめる。それが教育であり、指導だ」というのです。
平澤興先生は、「教育とはいかに相手をほめるかの研究である」「なによりも大切なことは、人を生かすことである。そして、その人に喜びと勇気と希望を与えることである」「あなたは、あなた自身が知らないところの、数倍のかくれた素晴らしいものを心の中にもっておる。/とにかく、自身をもって堂々とおやりなさい」
会長先生は、「人を育てるとは仏性の自覚を促すこと、そしてほめるとは、その相手の仏性を信じることのように思えます」と。
会長先生のお言葉を伺って私の心は、じ~ん仁。じわ~と愛と信頼が湧き出て、そして、ほっこり…。
・信じて拝む
では、どうすればいいのか――
やってみせ、言って聞かせてさせてみて、ほめてやらねば人は動かじ
話し合い、耳を傾け承認し、任せてやらねば人は育たず
やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば人は実らず山本五十六
やはり、相手の仏性をとことん信じて拝む姿勢が、人を育てるうえでは大切なのです。また、ここには「あなたのことが必要なのだ」という愛情や信頼も見てとれますが、自分の価値に気づかせ、生きる喜びと希望や勇気を与えるそうしたふれあいは、同時に「私もこの人のようになりたい」と願う心に導くものです。
日々の精進~「信者さんから聞かせていただいたお話から、私が何を功徳として頂戴できたかを伝えることが、その方をほめ称えること」→→自他の仏性を信じて拝みきれるよう、自らの心が素直でないと、相手をほんとうにほめることはできないという大事なことを教えています、と会長先生のお言葉です。
自分の心が「素直」でないと、ほんとうに人をほめることはできないなぁと、腑におちました。そして、「素直」の時は、自分の心も嬉しく楽しくなります。
今夏は、心のアセをたくさん掻いて「ほめまくり」「ほめちぎり」「ほめたたえる」私を目指したいです。秋の豊かな収穫を楽しみに「心田を耕す」&「心田に水を湛える(たたえる)」だけです。では、お盆過ぎの涼風のころ、笑顔でお会いしましょう。
令和七年八月
立正佼成会仙台教会
教会長 岩間由記子
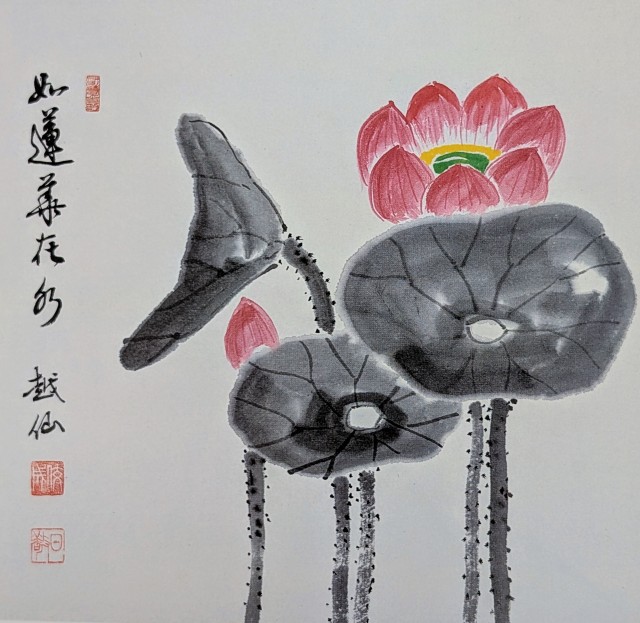
庭野開祖さまの書画(画像はイメージです)