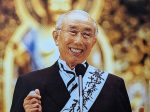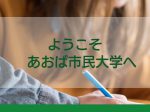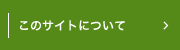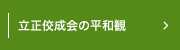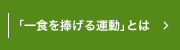💎 庭野日敬開祖「一日一言」~毎日のことば~(令和6年12月)
- 2024/12/1
- 心を創る
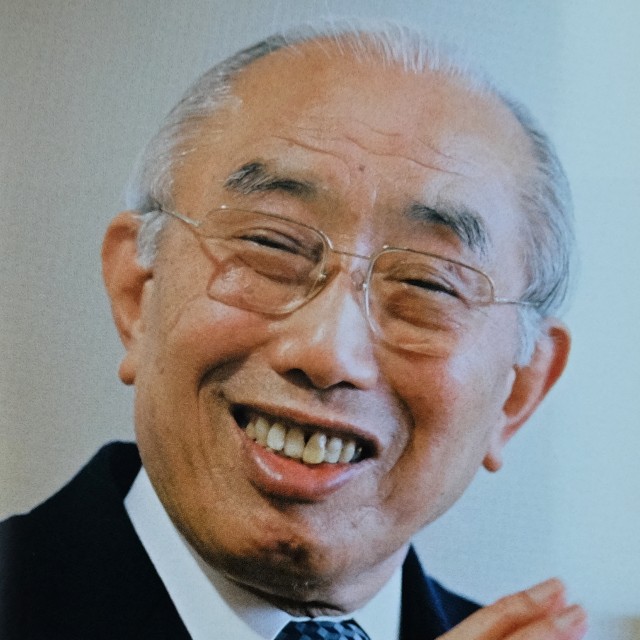
今年も「師走」を迎えました。今月も庭野開祖の折々のことばを、「一日一言」と題して毎日1つずつご紹介していきます。
【12月31日 愛するとは】
愛するとは受け入れること、大切にすること、と言ったほうがよく分かる気がします。(『開祖随感』8巻より)
【12月30日 私の流儀】
「いいことだ」と思ったら、その日から実行するのが、私の流儀です。(『開祖随感』8巻より)
【12月29日 一つの実行】
信仰は、たくさんの知識より一つの実行です。わが身をもってつかんだ感動こそが大切なのです。(『開祖随感』8巻より)
【12月28日 「はい」、「ありがとうございます」】
家庭でも職場でも、「はい」という返事、「ありがとうございます」という感謝の言葉が自然に出てくるようになると、あの仏さまの美しいお姿が、だんだん身に具わってきます。(『開祖随感』8巻より)
【12月27日 仏性を認めるとは】
あやまちまでも含めて、その人をそっくり受け止めてあげるのが、すべての人の仏性を認めることなのですね。(『開祖随感』8巻より)
【12月26日 自分が信じる】
人が自分を信用してくれない、とぼやく人を見ていると、自分も相手を信用していないのです。(『開祖随感』8巻より)
【12月25日 人生を拓(ひら)く切り札】
ご法の縁に触れた私たちは、毎日「自分が変われば相手が変わる」と聞かされ、それをごくあたりまえの、なんでもないことのように思っていますが、これこそ人生を拓く切り札なのです。(『開祖随感』8巻より)
【12月24日 人の生かし方】
人の生かし方でも、悪いところをいちいち注意するより、相手の得意な面をほめてあげたほうが、ずっと効果が上がります。(『開祖随感』8巻より)
【12月23日 言葉の重み】
言葉の重みは、何を語るかでなく、だれが語るかにあります。神仏を信じ、その教えどおりに行じている人が語ると、かりに言葉は稚拙でも、「この人についていこう」という気持ちになるものなのです。(『開祖随感』8巻より)
【12月22日 平和づくり】
私たち宗教者の平和づくりは、人と人、国と国の信頼づくりです。神仏を信じ、人はすべて神仏の子だと信じきるその宗教心なしに真の平和は実現しない、と私は信じているのです。(『開祖随感』8巻より)
【12月21日 人間関係の出発点】
人間関係の出発点は、相手も自分と同じ喜びや悲しみ、願いを持って生きているのを知ることです。法華経の常不軽菩薩の仏性礼拝行も、それを心に刻みつける行といえましょう。(『開祖随感』8巻より)
【12月20日 平和づくりの早道】
お互いに、相手の弱点ではなく、長所を認め合う働きかけこそ平和づくりの早道でしょう。(『開祖随感』8巻より)
【12月19日 いちばんの宝物】
喜びの奉仕こそ、在家の信仰者のいちばんの宝物でしょう。(『開祖随感』8巻より)
【12月18日 法華経の根本】
法華経の根本は、調和の思想といってもいいでしょう。それを”統一”と考えると一つのものに統合するように誤解されかねませんが、法華経は、すべての存在を同根と考えるのです。(『開祖随感』8巻より)
【12月17日 信じて、勇気を持って】
信じて、勇気を持って一歩を踏みだすのが信仰です。(『開祖随感』8巻より)
【12月16日 人がついてくるような人に】
なんでも分かったようなつもりで「教えてやるんだ」という姿勢では、人はついてこない。自分では分かっているつもりの人ほど、人の心が分かっていないからです。(『開祖随感』8巻より)
【12月15日 縁起を見る】
ものごとを正しく見るためには、長い目で見ること、一面だけでなく多面的に見ること、枝葉にとらわれず根本を見ること、この三つをいつも心にとめておくことだ、といわれます。それが縁起を見ることなのですね。(『開祖随感』8巻より)
【12月14日 素直に正直に】
素直に、正直に自分をさらけだして、自分なりの人生の目標をつかむと、一日一日に張りが出てきます。(『開祖随感』8巻より)
【12月13日 素直②】
素直な心になると、仏さまのはたらきを目のあたりにできて、姿の見えない仏さまの存在が、はっきりと見えてくるのです。(『開祖随感』8巻より)
【12月12日 素直①】
信仰では、素直さがいちばん大事です。素直さこそ信仰の入り口であり、終着点だといっていいでしょう。(『開祖随感』8巻より)
【12月11日 心の底から】
心の底から相手に幸せになってもらいたいという願いから出た言葉は、ただひと言であっても、相手の琴線(きんせん)に触れて、人を動かすのです。(『開祖随感』8巻より)
【12月10日 欠点を長所にするウルトラC】
欠点を指摘するのは、だれにもできます。大事なのはその人の長所を見つけてあげられる目を持つことです。それが具わって初めて、人の欠点を長所に変えるという”ウルトラC”ができる幹部さんになるのですね。(『開祖随感』8巻より)
【12月9日 仏さまと同じ姿に】
家庭でも職場でも、「はい」という返事、「ありがとうございます」という感謝の言葉が自然に出てくるようになると、あの仏さまの美しいお姿が、だんだん身に具わってきます。(『開祖随感』8巻より)
【12月8日 世の中でいちばん強い人】
この世の中でいちばん強いのは、世のため人のために奉仕することを信念として生きている人なのではないでしょうか。(『開祖随感』6巻より)
【12月7日 宗教協力】
宗教が互いに協力するということっは、網の目を密にすることです。それでこそ全人類の心を包み、救うことができます。この地上に平和が築けるのです。(『開祖随感』6巻より)
【12月6日 自覚を持って】
あの人のやり方ではだめだとか、おれでなければだめだとかと言う人がおりますが、仏教徒としての自覚を持って、ただひたすら自分のなすべきことをなせばよいのです。(『開祖随感』6巻より)
【12月5日 精進】
人に言われて、仕方なく、嫌々やられる努力ではなく、自分がやりたくてやる努力、それが精進です。(『開祖随感』11巻より)
【12月4日 大もとは人の心】
社会や会社が突き当たる困難はさまざまですが、その大もとは人の心にあります。人びとを導くリーダーは、そこのところをしっかりと見すえなくてはなりません。(『開祖随感』11巻より)
【12月3日 説法②】
法と説くのには、まず相手にこっちを向いてもらい、心を開いてもらうことが大事です。そのためには、まず相手の言い分を「なるほど」と、うなずいて聞いてあげることから始めなくてはならないのです。(『開祖随感』11巻より)
【12月2日 説法①】
説法でいちばん大事なのは、「この教えを実践すれば、あなたもこんなに幸せになれるのですよ」という一念に尽きます。(『開祖随感』11巻より)
【12月1日 変化に動じないコツ】
なにごとにも勝負の分かれ目は、ツキが落ちたときをいかにしのぐかにあると言います。さまざまな変化に動じないコツは、目の前の現実をそのまま素直に受け入れることにあります。(『開祖随感』11巻より)